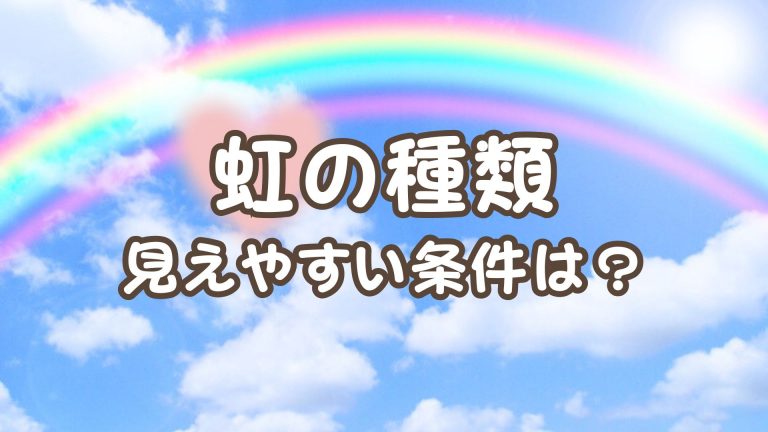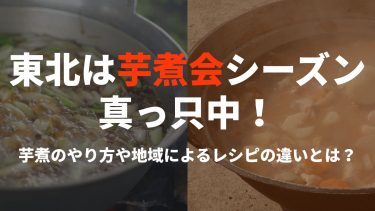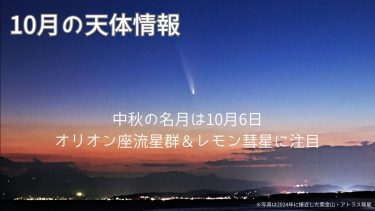春は空気中の水蒸気量が増えてきて、夏にかけて虹に出会える機会が多くなります。
立春・春分などの二十四節気をさらに三等分した七十二候が清明の末候である「 虹始見(にじはじめてあらわる)」(4月14日頃~4月18日頃)に変わり、冬に比べて虹が現れやすい時期となりました。
今日は、虹のメカニズムや空で見られる虹色の現象についてお話しします!
虹とは?メカニズムや色の順番
虹は太陽の光が空気中の水滴で屈折(折れ曲がる)・反射(はね返る)して起きる現象です。
色の順番は、光の波長の長さの順に、虹の外側から内側にかけて赤、だいだい、黄、緑、青、藍、むらさきと日本では7色になります。
主虹と副虹

この主虹(しゅにじ)の外側にもう一つ虹が見え、「ダブルレインボー」ということもあります。この外側の虹を「副虹(ふくにじ)」と呼び、主虹に比べて色がぼんやりと見え、色の順番が先ほどあげた主虹の順番とは逆になります。外側が紫~内側が赤となり、光の屈折が2回起こるためです。
虹が出やすい場所
虹は必ず太陽を背にした方向に現れます。
虹が見られやすい条件は、①空気中に水蒸気(水滴)がある。②晴れていて太陽の光が差し込んでいる。③太陽の高さが低い方が見えやすい(朝や夕方など)などがあり、雨上がりの晴れた時間に見られやすいのは、空気中に水蒸気が多く含まれているためです。
虹と虹のようなもの(暈・幻日)
主虹や副虹のほかにも、空で見られる虹のような現象があります。
暈、幻日、環水平アーク、環天頂アーク、彩雲などがあり、これらは「大気光象」という現象にまとめられます。
「暈」とは?太陽や月の周りにできる虹色の輪で天気が崩れる前兆?

暈(かさ)とは、太陽や月の周りに薄く現れる光の輪のことです。空の高いところに氷晶(こまかい氷の粒)からなる薄い雲(上層雲)が広がっているときに、雲の中に含まれる氷晶による光の屈折が原因でできます。
太陽の周りにできるものを「日暈」や「ハロ」、月の周りにできるものを「月暈」と呼び、屈折率が小さい赤色が内側、紫色が外側となります。
日暈が見られるとラッキーな気持ちになりますが、実は天気が崩れる前兆とも言われています。雲が厚くなると低気圧や前線が近づき天気が下り坂になるため、注意が必要です。
レア度がやや高い「幻日」

幻日(げんじつ)とは、太陽と同じ高さの左右の位置にできる明るく色づいた光の点で、こちらも氷晶による光の屈折でできます。太陽高度の低い朝や夕方に見られやすい現象です。
環水平アーク

環水平(かんすいへい)アークは、太陽から下方に、水平にのびる虹色の帯が見える現象です。こちらも太陽の光が空気中の氷の粒によって屈折することでできます。太陽の高さが高いとき、つまり、6月の夏至を中心に3月~9月頃の正午近くが現れやすい条件となります。
環天頂アーク

一方、環天頂(かんてんちょう)アークは太陽のはるか上方に虹色をした弧を描く光の帯です。通常の虹と逆さの向きに見えることから「逆さ虹」ともよばれます。
環天頂アークは環水平アーク同様、空気中の氷晶によって太陽光が屈折することで現れる現象であるため、氷晶からなる上層雲が現れているときに見られます。
環天頂アークは太陽と天頂の間に現れるので、太陽の高さが低いとき、つまり、季節を問わず、朝や夕方に見られやすくなります。
虹色に色づく雲「彩雲」

晴れた日の空に、虹色に輝く雲がみられることがあります。
このような雲を「彩雲(さいうん)」と言います。
彩雲は、太陽の光が雲の中に含まれる水滴を回り込むことで発生します。水滴を回り込む際に、赤い光は波長すなわち「波の長さ」が長く、青い光に比べて、より大きな角度で進みます。太陽の光が水滴を回ることによって、色ごとの光の波長の違いにより、色が分かれて見え、雲が虹色に見えるのです。
発生しやすい条件としては、太陽の近くに「巻雲」や「巻層雲」、「高積雲」といった、比較的薄い雲が広がる場合です。雲の見分け方は、こちらのコラムで確認してみてください。彩雲を探す際は、太陽を直接見ないように気を付けましょう。
【参考資料】
・気象庁「雲・大気現象・大気光象について」
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/faq/faq13.html